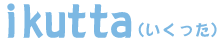最近の育児書には「トイレトレーニングは焦らずに」と書いてあることが大半ですが、1歳を過ぎると
「そろそろトイレトレーニングやるの?」
なんて会話がちらほら耳に入ってくるようになり、焦りを感じているママもいらっしゃるのではないでしょうか。
特に我々の親世代は『おむつは布、トイトレは1歳代で終了』が当然だったという人も多いので、お義母さんから「まだおむつなんてしてるの!?恥ずかしい!」なんて余計なプレッシャーかけられて困ってる・・・なんて声もよく聞きます。
しまじろうのDMに『1歳、この夏勝負のおむつはずし!』なんてキャッチコピーが踊っていたり、一部メディアで『おむつなし育児』がもてはやされた影響もあり、1歳の夏を迎えると
「そろそろやらなきゃまずい?おいてかれる?」と何だかそわそわしてしまいますね。
そこで、実際のところどうなの?といろいろ調べてみました。
また最後に、上記のプレッシャーに見事に踊らされた、私のおむつはずし体験記も載せてみました。
よかったら参考にしてみてくださいね。
スポンサーリンク
1歳代でトイトレを始めるための条件は?

まずは、1歳代でトイトレを始めるための条件について、手元の育児書には
- おしっこの間隔が一定時間以上あくこと
- あんよができること
- 単語が数語でも話せ、大人の出す簡単な指示に従えること
などの条件が揃っていれば、トイトレを開始しても大丈夫とあります。
おしっこの間隔があいているかどうかは、まめにおむつをチェックするしかありません。
けど紙おむつって、はっきり言って性能よすぎて出てるかどうか分かりにくくないですか?
そういうときはいっそのこと布おむつや普通のパンツをはかせてみるとわかりやすいです。
ということで、『1歳代のトイトレはおもらしとワンセット』だと覚悟してください。
『トイトレは夏が最適』といわれているのはなぜ?

では、なぜ1歳の夏になるとみんながそわそわし始めるのでしょうか。
それは、『トイトレの最適期は夏』というのが定番だからです。
夏場なら、洗濯物の乾きが早いので、布パンツをどんどん汚してどんどん洗濯しても、そんなに苦になりません。
また、家の中ではいっそのことパンツ1枚とか、Tシャツのみなんて荒業も、暑い夏ならやりやすいですよね。
おしっこ出そう→おしっこ出た、という感覚を身に着けるには、紙おむつでは難しいので、布パンツで過ごしやすい暖かい時期を狙ってトイトレする人が多いのはこういう理由からです。
実際の進め方は?

1歳代でトイトレを始める場合、一般的な方法は
- トイレに慣れさせる
- 便座に座らせてみる。出たら大げさに褒める
- タイミングをみてトイレに連れて行く
という感じですね。
タイミングを見て、というのは『起床後』『ご飯、お風呂の前』『もじもじしていたとき』などが挙げられます。
子どもの出すサインを見逃さないで、なんて言われますが、これがなかなか至難の技。
結局、生活の決まった節目でというのが無難です。
「トイレは怖くない」「トイレでおしっこできたら嬉しいし気持ちいい」というのを分かってもらうのが目的なので、一応トイレやおまるに誘ってみても嫌がったり、座ってみたけど出なかったらさっさと終了し、無理強いしないようにします。
『早期トイレトレーニング』『おむつなし育児』ってホントにできるの?

育児書によっては、『早期トイレトレーニング』『おむつなし育児』なんていうのも耳にします。
曰く、
- 赤ちゃんの排泄感覚を正常に働かせれば誰にでも簡単
- おむつでお尻が濡れた状態で放置するなんて赤ちゃんが可哀そう
とか、さもおむつは悪、1歳前でも取るのが当然、取れないのは親の怠慢みたいに言われてますね。
でも、ママの置かれている環境とか、赤ちゃんの発達とか、いろんなものが絡んでくるので、一概に必ず成功するとは言えないんじゃないかなあと思います。
赤ちゃんだけに集中できるとか、ママの他にも大人の手があるとか、できそうな環境が揃っていればやってみる価値はあるかもしれませんが・・・
あくまでも個人的見解ですけど。
実録!我が家のトイトレ体験記
我が家は1歳夏説にまんまと踊らされて、子ども8ヶ月の夏と1歳8か月の夏、トイトレにチャレンジしています。
1回目:8か月の夏。
たっちができたくらいでしたが、ジジババの「昔は」攻撃に流されて、とりあえず開始しました。
まず、おしっこ出た、を分からせるため、お風呂でおしっこしたら「ちーでたね」と声をかけました。
同時に、おまるを購入。起きた時、ご飯の前に座らせると決めました。
「おしっこ」の存在は、ほどなくして理解してくれました。
機嫌がいいと「ちー」と言ってくれたし、おまるでも、最初数回はうまく出せました。
これで調子に乗った私は、思い切ってパンツにする!と決意。
トレパンやら布パンツやらを大量購入しました。
ところが、ここからがうまくいかない。
おしっこした10分後には、またパンツが濡れています。
慌ててパンツを替え、おまるに誘導しますが、嫌がって座ろうとしません。
諦めたその10分後、またパンツが濡れている・・・この繰り返しで、大量にあったはずのパンツは、1日ですべて洗濯機行きに(涙)
そのため、「今日はパンツ」「今日はおむつ」とブレブレで一定せず、子どももさぞ混乱したと思います。
ご褒美のシール作戦も全く喜ばず、アンパンマンやわんわんのポスターも効果なし。
というわけで、涼しくなる頃にトイトレの一時中断を決意しました。
2回目:1歳8か月の夏
とりあえずトイレに行く、便座に座る、ということろまではクリアしました。
が、10分おきのちょろちょろおしっこは相変わらず。
ほぼ同じ経過を辿り、嫌になってやめてしまいました。
結局、我が子がおむつを外せたのは幼稚園に入園した3歳半のとき。
このとき一応日中のおむつは外せましたが、ちょこちょこおもらしが続き、完全におもらしもしなくなったのは年長の時でした。
小児科のドクターや心理士さんなどにも相談しましたが、我が子の場合、膀胱の発達がかなり遅かったようです。
下の子は2歳前にほとんど取れてしまったので、本当にこればっかりは個人差なんだなあと感じました。
多分、上の子のような場合でも、こまめにトイレに連れて行く余裕が私にあれば取れたかもしれませんが・・・
せっかく楽しそうに遊んでいるのに10分ごとに無理やり中断させるのは可哀そうな気がしたし、何よりそこまでトイレに懸ける情熱がなかったのが敗因かもしれません。
まとめ
- 1歳代でおむつを取るにはそれなりに親の根気が必要
- 決まったタイミングでトイレに誘って、嫌がったらすぐ切り上げる
- 遊びの延長で楽しく進める
- 子どもの発達次第では成功しないこともある
というわけで、1歳代でのトイトレは「焦らず、楽しく、気楽に」。
育児書通りに進めても成功しない子もいるので、あくまでも「外れたらラッキー」くらいの気持ちで臨むのがよさそうです。
あまり情報や周りの声に流されず、その子に合った方法で進めてあげてくださいね。