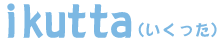3歳くらいになると、おしゃべりも上手になってきて、子どもとの会話も楽しくなってきます。
一方、ちょっと気になる話し方をする子も少なからず存在します。
こちらの意思は通じてるのになかなか自分から話さない子、冒頭や途中で詰まってしまってスラスラ話せない子・・・。
実は我が子、後者のタイプでした。
いわゆる吃音(きつおん)ですね。
※「どもり症」とも言います。
そして、何を隠そう、私自身も筋金入りの吃音持ちです。
そこで今回は、この吃音について、我が子と自分自身の体験談を交えつつ、お話してみたいと思います。
少しでも我が子の吃音に悩むママたちの参考になりますように。
スポンサーリンク
吃音の2つのタイプ
一口に吃音といっても、大きく分けて2つのタイプに分けることができます。
① 冒頭の発音が苦手なタイプ
例:「………っりんご!」
② 途中の発音を繰り返すタイプ
例:「りりりりりんご!」
必ずしもどちらかだけが現れるわけではなく、言葉によって①だったり②だったりという場合もあります。
なぜ起こるの?治し方は?
吃音が起こる機序はまだ明らかになっていませんが、原因として考えられるもののひとつとして挙げられるのは、過度のストレスです。
我が子に吃音が出始めたのも、思い返せば幼稚園入園前でした。
治療法は特にありません。
上手につきあいながら、収まってくるのを待ちます。
接し方で注意する点は?
吃音が早く収まるかどうかは、まわりの人々の接し方によるところもあります。
これは言語療法士さんに言われたことですが、吃音が早く治まるようにするためのコツは、
- 指摘しない
- 言い直させない
この2点に尽きるそうです。
つまり、いくら気になったとしても
「りんごでしょ?り・ん・ご!言ってごらんなさい」
なんてやるのは逆効果なわけです。
「ああ、りんごね。はいどうぞ。」と、何事もなかったかのように接してあげてください。
伝わった!という安心感が、次の発語に繋がります。
私たち親にできること

子どもが顔を真っ赤にしてどもっているのを見ると、「親として何かできることはないのか?」と悩みますね。
そこで、当事者として、また吃音児の親として「子どもにしてやれること・してほしいこと」を書き出してみます。
① 本人には「なかったこと」に
先述したように、本人には何事もなかったかのように接するのが一番です。
一番傷ついてるのは本人なので、これ以上指摘しないであげてください。
② 保育園・幼稚園には事前に伝えておく
話し方がスムーズでないと、やはり小さな子ども同士、いじめやからかいに繋がりかねません。
保育園・幼稚園には必ず現状を伝え、しかるべき対処をお願いしてください。
③ 親の相談先を確保しておく
- 今の接し方が正しいのか?
- 今後の見通しは
など、やはり親も不安になるもの。
自治体の育児相談室などに定期的に相談しつつ、何かあればいつでも言語療法士さんに繋いでもらえる環境を作っておくと安心です。
④ 早期療育は内容による
昨今、発育に不安があるとすぐに療育へ、という流れが定着しつつありますが、私の個人的な考えとしては、心配事が吃音のみならば無理に療育など特別な環境を用意する必要はない、と考えています。
なぜなら、そこで発音などの練習をさせられるのは、かえってプレッシャーを与える結果になりかねないからです。
吃音のことは置いといて、親子でふれあいながら子どもに自信をつけさせたり、親がこっそりと相談できたり…という親子教室的なものなら大丈夫かもしれませんが、それが吃音のために行っていると子どもに悟られないように配慮してあげてくださいね。
私としては、それよりも、子どもの得意そうな分野の習い事などで自信をつけさせてあげたほうがいいのでは?と思っています。
吃音持ちだった学生時代を振り返ってみる

かれこれウン十年、筋金入りの吃音持ちな私。
そんな私の、吃音にまつわる思い出をいくつか書き出してみます。
ビデオが嫌い
発表会など、ビデオ撮影されるのは本当に大っきらいでした。まさに現実逃避(笑)
音読がラップ調
小学生になると避けて通れない音読。
どうしても苦手な発音のところは、節をかえたりリズムをつけたり、まさにラップ状態(笑)
あとやたらと感情的に読んでみたりとか・・・
悟られないため結構必死でしたが、特別扱いされなかったのが私の性格的には合っていました。
友人に変なあだ名をつける
どうしても発音しにくい名字のクラスメイトは、名字で呼ぶことを放棄し、変なあだ名を勝手に付けて呼んでました(笑)
どうでしょうか?
たとえ吃音が長引いたとしても、それなりに工夫して何とかなるものです。
対処法は本人がいろいろ工夫して編み出していくので、周囲の大人の方はもう、信じて見守ってあげてほしいですね。
それから・・・
もし将来、吃音のために夢を諦めようとしてたら、そこだけはガツンと叱ってやってください。
私自身、それだけがとても心残りなので。
まとめ
- 吃音は本人には指摘しないのがベスト
- 保育者には必ず伝え、協力をお願いする
- 親が悩みすぎないよう、相談先を見つけておく
- 長引いてもそれなりに何とかなるが、周囲の心遣いとさりげないサポートは必須
話すことは日常生活を送るうえで避けては通れないので、吃音があるとどうしても目立ってしまいがち。
幼くても、本人なりにとても気にしていると思うので、周りの大人が正しい知識を持って、子どもの心に寄り添ってあげてほしいです。
この子の吃音はいつ治まるのか…それは神のみぞ知る。
けれど、周囲の適切なサポートがあれば、たとえ長引いても、充実した生活をおくることは可能です。
どうか焦らず気長に。
「吃音があるけど自分の事嫌いじゃないよ」と自信をもってもらえるよう、のんびり付き合っていきましょうね。