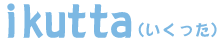2歳前後になるとやってくる、恐怖のイヤイヤ期。
何でもかんでも「これイヤ!」「あれイヤ!!」とやられては、相手をしている大人のほうが「もう嫌!!」と参ってしまいますね…。
ただ、そのイヤ!に隠された子どもの本音、あなたは見抜けていますか?
イヤ!!には大きく分けて
- 自分でやりたい、自分の思い通りになってほしい!という自我の目覚めからくる「イヤ」
- どうしても耐え難いことから逃れたい「イヤ」
の2種類があります。
俗にいうイヤイヤ期は主に前者のほうを指しますが、中には後者のイヤイヤも混ざっているので要注意です。
今回は、後者のイヤイヤのひとつ、『感覚過敏』について、みなさんにぜひ知っていただきたいと思います。
スポンサーリンク
『感覚過敏』って言葉、知ってますか?

感覚過敏とは、光(視覚)や音(聴覚)、触覚や味覚など、さまざまな『感覚』を人より過剰に受け取ってしまう状態のこと。
私たちが想像できないような現れ方をすることもあり、その存在を知っていないと単なるわがままに映ったり、子ども本人が多大なストレスを抱え込むことになりかねません。
また、逆に感覚の鈍感さ(感覚鈍麻)を抱えている子も。
どちらも、感覚に偏りがあることが原因ですが、本人の生きづらさに加えて、周囲の理解を得られにくいという問題もあり、特に子どもが小さいうちは親の理解とフォローが欠かせません。
『感覚の偏り』には4つのパターンがある

感覚の偏り、といっても私たちには理解が難しい部分もありますが、問題の起こりやすい傾向として大きく4つのパターンに分類することができます。
以下、パターンとその特徴、現れやすい困りごとについてまとめました。
少し難しい専門用語が並んでいますが、その特徴だけでも押さえておくことで、子どもの困った行動の『本当の理由』がみえてくるかもしれません。
感覚過敏
感覚刺激に対して、過剰に反応する。
→特定の音や刺激が苦手、ちょっとした変化に弱くすぐ癇癪を起こす、偏食が激しい など
感覚回避
苦手な刺激から逃げようとする
→服や靴下などを着たがらない、のりや粘土・土などがさわれない など
感覚鈍麻
刺激に対する反応が弱い
→おもらししても気づかない、怪我や病気などの痛みが分かりにくい など
感覚探求
感覚への反応が弱いため、より強い刺激を求めてしまう
→壁や地面に頭を打ちつける(自傷行為)、くるくる回る(常同行動) など
お子さんの困りごとについて、当てはまる部分はありませんか?
感覚の偏りからくる困りごと…実はこんなところにも!!

「すぐ癇癪を起こして手がつけられない…」「わがままになった」と大人もお手上げのその症状、実は感覚の偏りからきてるのかもしれません。
上にも例としていくつか挙げましたが、他にもこんな困りごとはありませんか?
お祭りやショッピングセンターのような場所に行くと、グズグズが収まらない…
私たちの脳は、自分に必要な刺激を自動的に取捨選択しています。
しかし、刺激を均等に拾ってしまうタイプの子は、話し声やバックミュージック、右往左往する人々やお店など、すべての刺激を均等に拾ってしまいます。
そのため「うるさい!!」「目がチカチカする!!」と癇癪を起こすのです。
それが一部屋にたくさんの園児が集まる園生活などで表出すると、その嫌悪感をうまく表すことができないため周囲の子に当たってしまい、「すぐお友達トラブルを起こす子」とレッテルを貼られてしまうことも。
逆に、過度の刺激を求めるがあまり、お友達にべたべた触ったり、椅子にじっと座っていられなかったり…という問題が起こる場合もあります。
公園に連れて行っても遊具で遊んでくれない/遊具から離れてくれない
平衡感覚に過敏があると、揺れるものや高いところ、ふわっと落ちる感覚などが苦手です。
そのため、せっかく公園に連れてきたのにブランコも滑り台もやりたがらない…なんてことに。
また、土のざらざらした感覚が苦手だと、砂遊びもできません。
反対に、感覚の鈍さから過剰な刺激を求める『探求行動』から、揺れる感覚が楽しいブランコにやたら固執してお友達に貸してあげられない…なんてトラブルも。
人が多いショッピングモールの遊び場などでは、視覚や聴覚の刺激から遊べなくなる子もいます。
同じ遊びばかりにこだわる
例えばブランコばっかり乗りたがる、トミカを並べて遊ぶなど、遊ぶパターンが決まっていて、それを止めたり邪魔したりすると怒る、なんて場合。
探求行動によるもののほか、「余計な刺激をシャットアウトしたい(=感覚回避)」心理の現れであることも…。
また、「同じ」へのこだわりは、例えば
- 行ったことのない場所(旅行先など)でパニックを起こしやすい
- いつも同じ服ばかり着たがり、洗濯すると怒る
などといった困り事を引き起こすことも。
とかく刺激の多い感覚過敏の子にとっては、「いつもと同じ」が何よりなのかもしれませんね。
『感覚の偏り』にはどう対応したらいい?

では、子どもの困った行動が感覚の偏りからくるものかも?と思った場合、どのように対応したらいいのでしょうか。
苦手なもの・ことを把握する
困った行動を起こした場所、時間、前後の流れなどを思い起こして記録してみると、癇癪を起こしやすいシチュエーションが見えてきます。
それが子どもの嫌がる刺激に繋がっている場合は、過度に刺激にふれないようにしたり、刺激を緩和させる方法を考えることで、癇癪や他害(他者を傷つけること)を予防することができます。
具体的には、
- ショッピングモールなどへのお出掛けは比較的すいている平日にする
- 体調の悪い時、眠い時間帯などは避ける
- 身に着けるものは子どもの好む素材を選ぶ
などです。
その際、決して大人の尺度でだけ物事を判断しないようにしてくださいね。
- これくらいは出来て当然
- みんなと同じように出来ないのは恥ずかしい
という思いから、「みんなと同じ」を押し付けすぎると、子どもは傷つきます。
「刺激に慣れさせよう」としない、過度に避けようとしない
慣れれば平気になるはず、と嫌がっているのに無理強いするのはNG。
例えば黒板に爪を立てて「キ~~~ッ」とされているところを想像してみてください。
慣れるまで続けるぞ、なんて言われたらどう思いますか?拷問ですよね…。
ただ、かといって過度に避けるのもNGですよ。
感覚過敏は一般的に2~3歳がピークで、成長とともに徐々に緩和してくることも多いです。
- 癇癪に繋がりそうな場面では事前にこれからすることを予告する
- 参加できる部分だけでも参加してみる
など工夫していると、そのうち大丈夫になってた、ということも。
実は我が子も2歳ごろ、着衣に関する過敏があり、雪が降るまで長袖が着れませんでした。
調子が悪いと靴下もダメ、靴すらダメ。
身体を締め付ける感覚が嫌だったのかもしれません。
その年は本当に苦労しましたが、次の年の冬には普通にジャケットなども着てくれて、ほっとしたのを覚えています。
(多少好き嫌いはありましたが…)
相談窓口を確保する
困ったときにいつでも相談できる場所を確保しておくことは、ママの心の安定にも大切なこと。
ママ友だけでなく、自治体の保健センターや福祉課、子育て支援センターなど、公的機関に繋がっておくといざという時に安心ですし、場合によっては、病院や療育施設などに繋いでもらうこともできます。
決して一人で抱え込まないでくださいね。
まとめ
- 困った行動や癇癪は、『感覚の偏り』から起こる場合もある。
- 感じ方は人それぞれ。困った行動の裏には『子どもの困り感』が隠されていることも。
- 「これくらいは出来て当然」「わがまま言うな」で物事を終わらせないで。
- 状況をよく把握し、困り感を緩和させる方法を模索しよう。
- 2~3歳がピーク。成長とともに多くはだんだん薄れてきます。
(もしくはうまく付き合えるようになります) - ママが一人で抱え込まず、相談できる場所を確保すること。
何でこんなことばっかりするの!?と怒りたくなる場面にも、実は子どもの「困った!助けて!」が隠れていることがある、ということがご理解いただけましたでしょうか?
癇癪やトラブルの際には、ぜひ冷静に「なぜこの子はこんな行動をとるんだろう」と考えてみてあげてください。
意外と、そこに鍵が隠されているかもしれません。
また、感覚過敏というと発達障害とか何か病気のように捉えられがちですが、ひとつの『状態』であり、性格のようなもので、決して悪いものではありません。
「この子はそういう子」となるべく肯定的に捉えて、気楽に付き合っていけるといいですね。